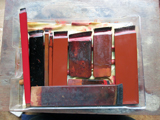漆のおはなし
日本を代表する工芸でありながら、漆については、案外知られていないことが多いのではないでしょうか。漆職人として、30年この生業に携わった経験から、漆についての様々なお話をまとめてみました。全11話構成です。
| 第1話〜第3話 | 第4話〜第6話 | <第7話〜第9話> | 第10話〜第11話(最終話) |
|---|
第7話 「漆も人間も下積みが大事?」 ― 漆の堅牢さを支える下地とは? ―
※画像をクリックすると 拡大します |
刻苧作業の様子 |
錆と錆付け作業の様子 |
漆の作業って、なかなか馴染みがない方にはわかりにくいですよね。これが陶芸なら、土を練って形を作り、窯に入れて焼く、ということは素人さんでもわかると思います。また織物なら、糸を染めて織機にかけ、縦糸と横糸を交互に絡ませながら織っていくことは、やったことがなくても大抵わかります。ところが漆の場合は、刷毛で漆を塗ることはわかっても、その前後の作業としてどんなことをするかは、実際やったことのない方には、よくわからないのではないでしょうか。
それでも、漆は何回も塗らなくてはいけないので、手間がかかることはご存じかと思います。「この品物は、何回くらい漆を塗ったものですか?」という質問をよく受けます。それに対して「数十回塗り重ねました」と答えると、「ほう、すごいですね。だからこんなに立派になっているのですね。値段も高くなるわけだ」というような感想が返ってきます。
けれど実際には、漆を塗り重ねた回数と、そのものの丈夫さ、美しさは、あまり関係がないのです。極端なことを言えば、技術が未熟な職人が失敗を繰り返して、何度も塗り直したものに、はたして価値はあるでしょうか。決めなければならないところを、きちっと一発で決め、最低限の期間で仕上げるのが、熟練した職人というものだと思います。
それでは、きちんと作られた価値の高い漆器というのは、いったい何が違うのでしょう? どういうところに手間をかけるものなのでしょう?
まずは、漆器は堅牢であることが一番だとぼくは思います。そしてその堅牢さを決めるものは、先回お話しした「素地」もさることながら、漆の「下地」にあると言っても過言ではないでしょう。
ではなぜ「下地」をしなければならないのでしょうか。たとえば一般的に、素地が木の場合を考えてみると、表面は平らなように見えても無数の穴や凸凹があり、そのまま漆を塗ると、漆が木に吸い込んでしまって塗膜ができなかったり、また木目や傷、板と板の合わせ目などが塗った面に現れたりして美しくないのです。
そこでまず、下地作業の最初に、「木落ち」と呼ばれる大きな傷や、板と板の合わせ目を丸い彫刻刀でえぐり、そこに「刻苧」(こくそ)というものをへらで埋めます。これは、水練り小麦粉と生漆(きうるし)を練り合わせた「麦漆」(むぎうるし)に、木の粉を飽和状態になるまで入れ込んだものです。次に、木地が破損しやすいような箇所(お椀であれば縁や底)に、麻布を漆で貼ります。(布着せ)。そのあと、「堅地」(かたじ)とか「錆」と呼ぶ下地を、粒子の粗いものから細かいものまで、順次、へらや刷毛を使って付けていきます。この下地は、「地の粉」(珪藻土を焼いた粉)や「砥の粉」(粘土を水漉しした微細な粉)を生漆と混ぜ合わせたものです。この下地を十分乾燥させてから、水をつけた砥石で研ぎ、表面を平らに滑らかにし、さらに生漆を吸い込ませて固め、仕上げとします。
この方法は、「本堅地」(ほんかたじ)と呼ばれる下地法で、かなり厚くはなるのですが、たいへん丈夫です。そのほかにも、何種類かの下地法があります。
ぼくの本業である「村上木彫り堆朱」は、木地にさまざまな文様を彫刻し、朱漆で仕上げるものですが、彫刻の部分には、文様が隠れてしまうため、布を着せたり下地を施したりできません。この場合は、生漆を毛の堅い刷毛を使って全面に摺り込みます。目いっぱい漆を吸い込ませて、彫りを漆で固めてしまうのですね。これはこれで、またとても丈夫なのです。
このように下地の善し悪しは、漆器そのものの価値を決めてしまうと言ってもいいほど重要です。よく仏具などに、「泥下地」というニカワで溶いた胡粉を塗っただけの簡略な下地をしたものがありますが、表面に塗った漆が何らかの原因で傷ついて、下地が表れたりすると、そこから水分などが入り込み、その周りまでどんどん剥がれ落ちてしまいます。ぼくも以前、漆の塗り直しを頼まれた仏具が、こうした泥下地だったために、それをすべて削ぎ落として、下地からやり直さなければならず、とても苦労をしたことがあります。
人間だって、ふだん豪華な衣装や化粧で本性が隠れていても、何かの折に、その人の持って生まれた品性や教養の有無が露見してしまうことがありますが、漆器もそれと同じなんですね。きちんとした下地が施されてさえあれば、表面の漆が傷ついても、塗り直すことで、また新品同様の輝きを取り戻すことが可能なのです。
ところで、この下地を含め、漆を塗るためには、さまざまな専用の道具が必要です。茶道の場合も、茶を点てる作法と同時に、お道具についての知識や扱い方がとても大切だと思いますが、漆職人の場合も、良い仕事をするためには良い道具が欠かせません。次回は、そんな漆の「道具」についてお話ししましょう。
第8話 「弘法も筆を選ぶ?」 ― 漆工を支える道具たち ―
※画像をクリックすると 拡大します |
篦 |
刷毛 |
砥石と木炭 |
これまで漆とはどういうものか、その性質や、漆器の素地、そして下地についてお話ししてきました。ぼくら職人は、漆について深く理解し、それをベストな状態で素地に定着させて、より堅牢で美しい漆器を作るために、日々精進を重ねています。
弘法大師のような書の達人は、どんな筆を使っても美しい書が書けると言いますが、これはほんとうでしょうか。漆の仕事をしていてぼくらが実感するのは、良い仕事をするためには、やはり良い道具が必要だということです。経験を積めば積むほど、道具を選ぶことの大切さがわかってくるような気がします。
漆を塗るためには、下地から仕上げまで、それぞれの工程に応じた実に多くの道具が必要ですが、もっとも基本的な道具は、「篦(へら)」「刷毛(はけ)」「砥石」の3つではないでしょうか。
まず「篦」ですが、これは漆を取り出したり、練り合わせたりするほかに、塗る場所に直接、漆や下地を引き渡したりするためにも使います。大まかにいうと、中塗りや上塗りをするための篦と、「錆」などの下地をつける篦、その他の篦の3つです。
中塗り、上塗りに使う篦は、少し堅めで弾力のある、チシャやイタヤカエデなどを削り、あらかじめ生漆を摺り込んでおいたもの。また下地用の篦は、下地の水分を吸ってくれるヒノキの白木が最適です。そのほか、小麦粉と漆、木粉を練り合わせた「刻苧」(こくそ)という充填剤をつけるための「竹篦」、塗り面の境からはみ出た漆を取り除くための「鯨篦」、より粗い下地をつけるための「金篦」などがあります。
さらにそれぞれ、用途に応じた形、幅、篦先の角度、堅さなど多種類のものを使い分け、その都度、砥石や刃物などで調整します。
次に「刷毛」ですが、漆を塗るための刷毛は、何の毛でできているか、おわかりでしょうか。その答えは「人間」です。いわゆる「人毛」ですね。しかも、一度もパーマをかけたことのない女性の、まっすぐで長い髪の毛でないとだめなのだそうで、現在はなかなか入手が困難なようです。
刷毛屋さんは、それを洗い、束ねて糊漆で固め、4枚のヒノキの板で挟んで仕上げ、ぼくら漆職人は、それに和紙や布を巻き、漆を塗ってから使用します。それは、毛にしみこんだ油が、刷毛の持ち手の部分に染み出さないようにするためなんですね。
刷毛は、毛が根元まで入っている「全通し」と、半分まで入っている「半通し」があり、また塗るものに合わせていろんな幅のものを使い分けますが、いずれも鉛筆のように、「塗師刀」を使って削り出しながら、短くなるまで使い切ります。削ったすぐは、毛の中の細かなゴミが出やすいので中塗り用に、何回か使用してゴミが出なくなったら上塗り用になるのです。そのほか刷毛には、粘っこい生漆を生地に摺り込むための堅い馬毛のものなども使います。
刷毛は使い終わったら、何度か菜種油をつけて堅い篦で突き出し、毛の部分をついた漆を完全に除去しておかなくてはいけません。この手入れを怠ると、毛先がガチガチに固まってしまうので、とくに注意が必要です。
3つめに「砥石」ですが、篦を調整したり、刃物を研いだりする大型のもののほかに、下地や漆面に直接当てて、表面を研ぐための多種類の小さな砥石があります。
漆は、1回塗って乾いたら、次の漆を塗る前に、必ず表面を研がなくてはなりません。そうしないと後々そこから剥げてしまいます。研ぐことで平らにすると同時に、表面を荒らして漆の食いつきを良くするのが目的なのですね。そのための砥石は、研ぐ面の形状に合わせて、台形のもの、尖ったもの、丸いもの、凹面のものなど様々な形のものを自分でつくっておきます。また上塗りした面を研ぐのは、砥石よりも傷がつきにくい、油桐などを焼いた専用の木炭ですが、これも砥石に当てて、自分で形を調整しながら使うのです。
漆の仕事は、塗っては研ぎ、また塗っては研ぐ、の繰り返しですが、塗るよりも研ぐ方が何倍も時間がかかります。この研ぎの善し悪しによって、漆器のグレードが決まると言っても過言ではないと思いますが、その研ぎを左右するのが、砥石なのですね。
以上このほかにも、ここでは説明しきれないほど、たくさんの道具を使いますが、いずれも、漆職人それぞれが自分で工夫して、自分専用のものを持っているので、職人同士で貸し借りすることはほとんどなく、またその道具を見れば、その人の腕前がわかると言われているほどです。道具は、武士にとっての刀と同じく、漆職人にとって「魂」と言われるほど大切なものだということを、おわかりいただけましたでしょうか。
さて次回は、「蒔絵」や「沈金」「螺鈿」(らでん)など、漆を塗った上に施される様々な加飾や、全国のいろいろな産地で行われている「変わり塗り」について、ぼくのわかる範囲でお話ししたいと思います。
第9話 「漆は怪人二十面相?」 ― 多彩な漆の加飾技法 ―
※画像をクリックすると 拡大します |
片輪車蒔絵手箱 |
蒟醤の銘々皿 |
津軽塗の茶托 |
つややかな漆は、特に何もしなくても、それ自体が美しいのですが、そこにさまざまな装飾を加えることで、更に多様な美の世界を作り出すことが可能です。それは漆が塗料であると同時に接着剤でもあり、何かを貼り付けたり、塗り込めたりすることができ、また塗膜の層を重ねることで、それらを研ぎ出したり、彫ったりもできて、じつに多種多様な加工ができるという、優れた性質をもっているからでしょう。まさに怪人二十面相のように、いろんな顔を持っている「謎の存在」と言えるかもしれません。
さまざまある漆の加飾で、最もポピュラーなものは、なんといっても「蒔絵」でしょうね。漆で描いた文様に、漆の乾かないうちに金粉や銀粉を蒔いて定着させる技法で、その原型は奈良時代に遡りますが、平安時代以降、国風文化の確立とともに、日本の漆器を代表するものとなりました。
これには、金銀粉を蒔いた上に上質な生漆を薄く引いて粉を固め、乾燥後に磨いて輝きを出す「平蒔絵」や、文様を高く盛り上げる立体的な「高蒔絵」、また粉を蒔いた後で全面に漆を塗り重ね、金粉や銀粉が出てくるまで研ぎ出す「研出し蒔絵」などがあります。また金粉にも、丸粉、平目粉、梨地粉、消粉などさまざまな形があり、粒子の粗さが号数によって決まっていますので、文様によってどの粉をどの場所にどのように使うかを考えながら蒔くのです。
いずれも、その時々の漆の乾きを判断し、ベストなタイミングで粉を蒔いたり、また蒔き付ける粉の粗密をコントロールしたりするのはもちろんのこと、細い蒔絵筆を用いて、強靱で奥行きのある線を引くには、かなり熟練した技が必要です。特に研出し蒔絵は、研出しをやめるタイミングを計るのが難しく、一番難易度の高い蒔絵と言えるでしょう。
この蒔絵と、ちょっと見た感じは同じように見える「沈金」(ちんきん)という技法があります。産地としては輪島が有名でしょうか。
蒔絵が筆で絵を描くのに対し、沈金は「沈金刀」という独特の彫刻刀を使って、地の漆面に細く鋭い線を彫っていくやり方で、その後、全面に生漆を引き、拭き取ります。そして彫った線の部分に金箔を押し込んだり、金粉を蒔いたりして余分な箔や粉を拭き取ると、漆が完全に拭き取れなかった線の部分にだけ、箔や粉が定着するというわけです。
また、塗り上げた漆の面に同じように線を彫ったあと、全面に色漆を塗り、木炭で研ぎ出すと、彫った線の部分にだけ色が残る、つまり彫った溝に色漆を埋めるという技法があり、これを「蒟醤」(きんま)と言います。多色を使うには、それぞれの色ごとに充填や研ぎを繰り返す必要があり、たいへんな手間がかかりますが、繊細な美しい表現が可能です。元々は、ミャンマーなど東南アジアで行われている技法なのですが、日本では、高松など香川漆器の代表として定着しています。なお香川漆器にはもうひとつ、何層にも塗り重ねた漆の層を彫る「彫漆」(ちょうしつ)がありますが、これについては、次回詳しくお話ししましょう。
接着剤でもある漆の性質を利用するやり方のひとつとして、「螺鈿」(らでん)があります。ご覧になったことがおありでしょうか。これは光沢のある貝を、彫り下げた漆器の表面に埋め込み、隙間を漆で埋めて平らにする技法です。使われる貝には、夜光貝、白蝶貝、黒蝶貝、青貝(カワシンジュ貝)、アワビ、アコヤ貝などがあり、漆の艶と貝の輝きが調和して、独特の世界を演出します。なお、貝の代わりに金属の板を埋め込む技法は、「平文」(ひょうもん)と呼ばれます。
このように、漆器の加飾にはじつに多くのやり方があるのですが、さらに全国各地にある漆器の産地には、それぞれ独特の「変わり塗り」が伝わっています。漆器の産地というと、輪島や会津などが有名ですが、そのほかにも東北の各県をはじめとして、全国にたくさんの塗り方や加飾法があります。これらは江戸時代以降、刀の鞘塗りや釣り竿の竿塗りから派生した、とてもユニークなものも多いようです。
2007年のNHKの朝の連続ドラマ「ちりとてちん」の中で、米倉斉加年さん、松重豊さん演じるヒロインの祖父や父が、若狭塗の箸塗り職人をしていたのをご記憶の方もいらっしゃるでしょう。卵殻や貝殻、松葉、籾殻などいろんなものを漆の中に塗り込んでいましたよね。青森県の津軽塗の一種「唐塗」(からぬり)も、わざと多色の色漆をまだらに塗って研ぎ出すことで、独特の斑紋がつくられますし、「七々子塗」(ななこぬり)は、漆を塗った後に菜種を蒔き、乾いてからそれを除去して、漆を塗り重ね、研ぎ出すという、まさに「変わり塗り」の典型と言っていいでしょう。
ここではとても全てを紹介できませんが、次回はわが郷土の新潟県に絞り、新潟漆器と村上木彫堆朱について、少し詳しくお話ししたいと思います。
| ← 第4話〜第6話 | 第10話〜第11話(最終話) → |
|---|